こんにちは。
けいです。
今日はNISAについて学んでいきます。

NISAってよく聞くけどなんだろう

NISAが何かはわからないけど聞くから始めてみたいって人はすごく多いよ
NISAとは
NISAは日本語で少額投資非課税制度といいます。
株や投資信託の運用において税金がかからない制度のことです。
通常投資を行い利益が出た際には税金を払わないといけません。
給料や相続などでお金が増えたら税金を払わないといけないのと同じですね。
投資でもお金が増えたら税金を払う必要があり、例えば株や投資信託の売却時であれば得た利益に対して20.315%もの税金が発生します。
もしも100万円の利益を生み出せたとしても20万円ほどは税金として手元から消えてしまうわけです。
これはとても大きいですよね。
しかしNISAを利用した運用で利益を出すことができれば本来支払うべき税金を払う必要がなく、全額自身で受け取りができるといった制度になります。
NISAのメリット
①非課税で運用ができる
前述の通り、NISAで行っている運用では税金を払う必要がありません。
利益から引かれる20%の税金は決して少ない数字ではありません。
手元に資金が残ることは次の運用に際しても重要なポイントであり、何と言ってもNISA最大の強みは運用益が非課税になることでしょう。
②少額から投資ができる
NISAはあくまでも制度であり、保有する金融資産は株や投資信託となります。
そのため購入に必要な金額も株や投資信託の購入時と同様となり、数万円の購入や積立であれば1,000円からでも投資ができるようになります。
NISAといった特別な制度を利用するからといって多大な自己資金を要するわけではないこともNISAのメリットの一つとなります。
③いつでも解約が可能
投資は長期の運用が推奨されているものと言えど、人生いつ何時なにが起こるかはわかりません。
不測の事態により資金の必要に迫られることもあるかと思います。
NISAの運用にあたって時間の制限は特に設けられていないため、解約を自由に行えることも安心できるポイントの一つとなります。
一度運用を行ったら5年間は引き出せないであったり、10年以内の解約は手数料が発生するであったり、そのような事はないのでご安心ください。
NISAのデメリット
①損益通算・繰越控除ができない
損益通算とは利益と損失を相殺することを言います。
簡単に表すと以下のような仕組みです。
例えば2つの投資信託を保有し同一年内に解約したとしましょう。
Aの商品では50万円の利益、Bの商品では20万円の損失があったとします。
Aの商品しか保有をしていなかった場合は50万円が課税対象となりますが、Bの損失を相殺することによって課税対象を30万円とするような仕組みです。
繰越控除とは年をまたいで相殺することですね。
投資における損失はこのような相殺に回すことができますが、NISAの運用で損失を出しても損益通算や繰越控除に利用できないことはNISAのデメリットとなります。
②ひとり1口座までの保有である
NISA口座はひとり1口座までとなります。
例えばA証券でNISAの運用を行っていたとしましょう。
何かしらの理由でB証券を開くこととなり、使い勝手が良かったのでB証券でもNISAを使いたくなりました。
しかしA証券でNISAを開いている以上、B証券ではNISAの運用を行うことができないのです。
その場合はB証券は課税口座の運用のみとするか、A証券のNISA口座を廃止してB証券へ移管する必要があります。
まとめ
今日はNISAのメリットを学びました。
デメリットもありますが、基本的にはメリットが大きい制度です。
利用していない方は積極的に活用していきましょう。

税金がかからないと言われるとそれだけで使いたくなるなあ

NISAを利用することで購入時手数料を無料とする金融機関もあったりするからもっとお得だね

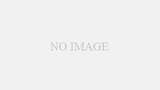
コメント