こんにちは。
けいです。
今日は投資信託を保有するにあたって発生するコストについて学んでいきます。

同じパフォーマンスでもコストによって大きく変わるから効率的な運用を目指したいね
購入時手数料
購入時手数料とは読んで字のごとく購入時に発生する手数料を指します。
こちらは購入金額に対して計算され、販売会社へ支払う手数料です。
ここで注意したいポイントは、同じ商品でも販売会社によって手数料の設定が異なるという点です。
投信は商品ごとに購入時手数料の割合が設定されています。
これはその手数料が発生するという意味ではなく、「その割合までなら購入時手数料として設定できますよ」といった意味なのです。
その定められた割合の中で販売会社はそれぞれ購入時手数料の設定を行います。
そのため購入したファンドの購入時手数料が別の販売会社を調べるともっと安かったという可能性もあるため注意しましょう。
また購入時手数料はそもそもかからない商品も存在しており、そのような商品はノーロードと呼ばれます。
信託報酬
信託報酬とは投資信託を保有している日々発生している手数料であり、運用管理費用とも呼ばれます。
先ほどの販売手数料とは異なり必ず発生する費用であり、販売会社・運用会社・受託会社のそれぞれに支払われます。
信託報酬は年率で表記が成されていますが実際は日々差し引かれているものです。
信託報酬の設定には幅があり、インデックス型のファンドは比較的低く、アクティブ型のファンドは比較的高く設定をされています。
ここでファンドを10年間保有した場合の手数料の差を単純計算で考えてみましょう。
信託報酬が0.1%のファンドを10年間保有した場合、10年かけて合計1%分の信託報酬を支払っている計算となります。
もしも信託報酬1%のファンドで10年間保有した場合は10%の信託報酬を支払っていることとなるため、ここで9%もの差が発生することとなります。
この差は小さくないため、このように考えると信託報酬は低いものを選んだ方が良いでしょう。
しかしアクティブ型は高いコストと引き換えに高いリターンを求める狙いです。
手数料以上に期待が持てそうであればアクティブ型ファンドを選ぶことも選択肢として良いでしょう。
信託財産留保額
信託財産留保額は解約時に発生する費用ですが、こちらは厳密に言うと手数料ではありません。
なぜならこちらは販売会社や運用会社、受託会社に支払う費用ではなく、ファンドに残していく費用となるからです。
信託財産留保額についても発生の有無はファンドによって異なります。
もしも信託財産留保額が無しのファンドを保有していた場合は解約時に引かれる費用が特にないということですね。
それでは信託財産留保額を支払うとはどのようなことなのでしょうか。
こちらの費用も割合で定められており、その割合に従って解約時に費用が一部引かれることとなります。
引かれた費用はファンドに残ることとなり、ファンドを運用するためのコストとして利用されます。
ご自身が解約される際には費用が引かれるので手数料のように感じるかもしれませんが、ファンドを保有している間は他の人が解約した際の費用を利用して運用を行っていたということですね。
そのように考えると信託財産留保額は一概に悪いものということはできないのです。(心情の観点からすると避けられがちであるように感じますが)
まとめ
投資信託を保有する際に発生するコストとして3つのコストがありました。
購入時に発生する購入時手数料。
保有時に発生する信託報酬。
解約時に発生する信託財産留保額。
それらの目的をしっかりと理解して効率的な資産運用を行いましょう。

購入時手数料はネット証券だとかからないことが多いからおすすめだよ

いきなりネットは難しそうだから最初は相談できると安心だな

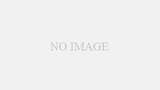
コメント